【その他】
【社中交歓】入
2025/04/17

いるまんじゅう
埼玉県入間市には、名産品の狭山茶をパウダーにして餡に練り込んだ「いるまんじゅう」という少しふざけた名の饅頭があります。
2012年、少年ジャンプNEXT!で入間市出身の大人気漫画家がコラボした作品『殺せんせーVS斉木楠雄~入間市最終決戦~』の中で、架空の名物として登場したのが「いるまんじゅう」でした。作品を見た全国のファンから商品化を望む声が市役所に寄せられる中、地元の中学生が書いた熱い手紙が市長を動かしたのです。そこで市が集英社に交渉するも商品化は難しいとの返答……。でもそこで終わらないのが入間市。だったら名前を変えて作ってしまえと、開発に10カ月もかけて「いるまのまんじゅう」として発売までこぎつけたのです。それを知った集英社から後日連絡があり、なんと公認で「いるまんじゅう」の商品化が決定、大ヒット商品となりました。
諦めずに挑戦すれば道は拓ける! さすが、我らがまち・入間市! ぜひそんな入間市にお越しいただき、狭山茶とともにお楽しみください。
蘇我入鹿を祀る神社
-

平越 真澄(ひらこし ますみ)
奈良三田会幹事、奈良まほろばソムリエ、サンスクリット塾主宰・1972文
『日本書紀』では逆臣であるとされ、乙巳(いっし)の変(645年)で殺された蘇我入鹿は、橿原(かしはら)市小綱町(しょうこちょう)入鹿神社に手厚く祀られています。この辺りは入鹿の母の出身地といわれ、今に至るまで入鹿は崇拝されています。入鹿は鶏の鳴き声を合図に首をはねられたといわれ、かつて小綱町では鶏を飼わなかったと伝えられています。
また、はねられた首が各地に飛んで行ったという伝説が残っています。興味深い話として、入鹿の首に追いかけられた中臣鎌足が、石舞台から談山神社に登る山道の気都和既(きつわき)神社まで逃げ込み、「もう来ぬだろう」と言ったことから、当地は「もうこの森」と呼ばれています。
入鹿贔屓の奈良県人の私は、敗者の入鹿を悪人として正史に記されたのではと思っています。『藤氏家伝』には入鹿の学問の師である僧旻(そうみん)が、入鹿のことを「鎌足の次に」優秀であると評しています。
今年の干支はまさに「乙巳」、入鹿に心を寄せたく思っています。
「何をやるか」よりも「誰とやるか」
-
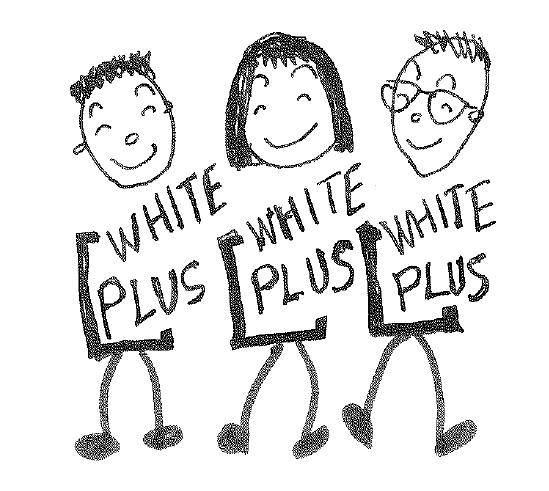
齋藤 亮介(さいとう りょうすけ)
株式会社ホワイトプラス取締役兼執行役員COO・2007経
私は「新しい日常をつくる」というビジョンを掲げ、「生活サービス×テクノロジー」領域でイノベーションを起こすべく、2009年に株式会社ホワイトプラスを起業しました。スマホで注文し、自宅にいたままクリーニングを出せる「リネット」を運営しています。今までにない新しいサービスを立ち上げ、世の中に広めていくには同じ志を持った仲間が必要です。そして社員1人ひとりに活躍してもらうために、入社時のおもてなしに力を入れています。
入社初日に渡している会社のロゴが入ったパーカーやバリューをデザインしたTシャツ、社史、名刺等を詰めたウェルカムキットは、入社時の期待感を高め、好評です。また各部門のオリエンテーション、ウェルカムランチも開催。先輩社員との交流を促進し、早期のチームビルディングに寄与しています。
「何をやるか」以上に「誰とやるか」が仕事のパフォーマンスに影響し、事業の成否を決めます。今後も社員同士の絆を深め、早く活躍する環境を整えることで、革新的な価値を世の中に広めていきます。
情報科の授業の変遷
-

西山 武繁(にしやま たけしげ)
慶應義塾幼稚舎情報科教諭
幼稚舎には1〜6年生までが学ぶ情報という授業があります。情報機器を使った表現活動とプログラミング学習が授業全体のテーマです。1年生の1学期は、その入門編にあたります。
授業にコンピュータを用いていた頃は、入門編らしい、初々しい光景を目にすることができました。授業ではじめてコンピュータに触れる児童が多く、マウスを思い通りに動かすことにも苦労しているようでした。マウスを思い通りに動かし、クリックができるようになること。それが1学期の目標でした。
2018年に1人1台のタブレットPC利用が始まると、入門編の様相は大きく変化しました。マウスで行っていた操作は直接画面に触れることで簡単に実行できます。クラスルームアプリを使い、絵を描く、文字を入力する、授業資料を見る、課題を提出するなどの方法を習得することが、1学期の目標となりました。1年生はあっという間にこれらを習得し、情報以外の授業でもタブレットPCを文房具の1つとして利用できるようになります。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

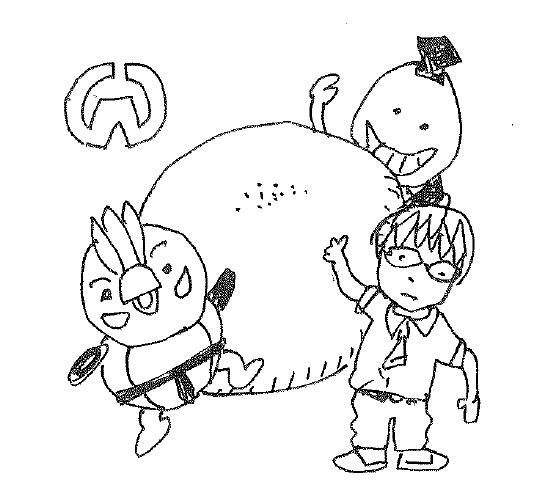
山岸 義弘(やまぎし よしひろ)
奥武蔵三田会会長・1969商