【その他】
【社中交歓】命
2024/12/26
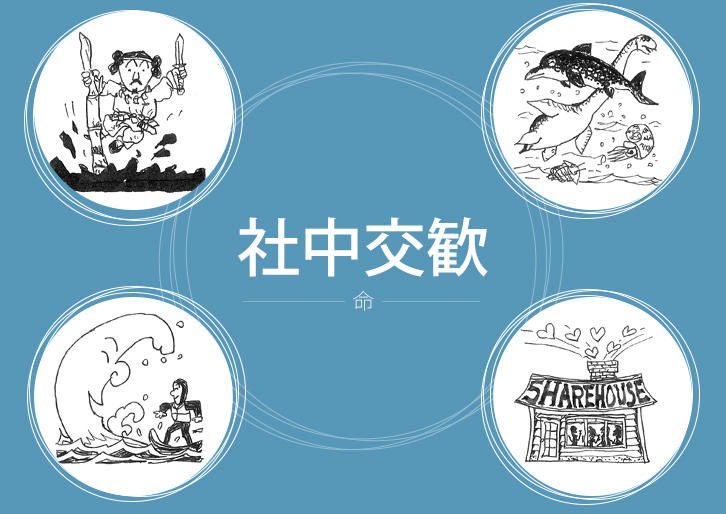
あしかびのおっさん
子どものころ、図鑑でストロマトライトというものを知った。大昔から酸素を生み出している、海中の塊らしい。命のみなもとがじっとした物体だという知識は、どうも実感のわきにくい驚きだった。
『古事記』神話の冒頭には、初発の国土が浮いた脂やクラゲのように漂っていた時、まず葦(あし)の芽のようなものができてウマシアシカビヒコヂという神になった、とある。かつて慶應義塾の教授だった折口信夫は、「おもろいあしかびのおっさん」とユーモラスに訳したそうだ(池田彌三郎『まれびとの座』)。
葦の芽に対する日本人の親しみは、大正2年の歌曲「早春賦」に「氷解(と)け去(さ)り葦は角(つの)ぐむ」(『日本歌唱集』)と歌われたことにも、現れているだろう。早春のどろどろした土壌から動物のツノのように飛び出す葦の芽への注意力が、古代からずっと保持されてきたことになる。自然科学の正確な知識とはまた別に、実生活の中から自らの目で生命のはじまりを見つけだし、それを毎年くり返し納得してきた、日本人の祖先の心意もまた、1つの真理だと思う。
海のまちで命を感じる
-
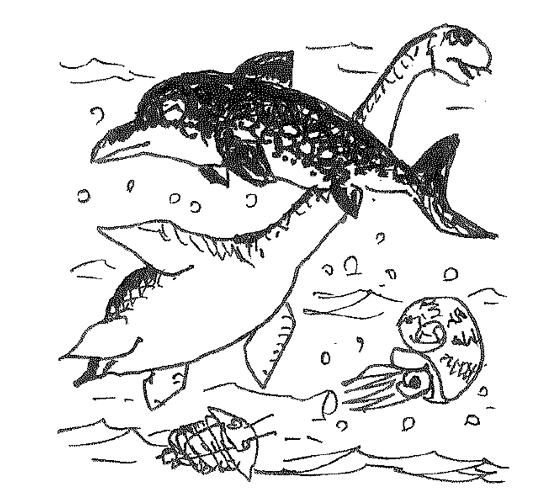
小池 健太朗(こいけ けんたろう)
小池商事株式会社取締役副社長、豊橋三田会幹事・2008経
愛知県蒲郡市は、穏やかな三河湾となだらかな山に囲まれた、温暖な観光地だ。人口8万人を切る小さなまちの駅から5分、海を目の前にして「生命の海科学館」はある。入ってすぐ目に入るのは、大きなクジラの化石だ。開館した1999年から公開された標本だが、なんとその後の研究の結果、新種新属であると認定された。そんな標本の飾られる1階の広々としたスペースでは、主に子ども向けのイベントが開催され、地元の親子連れが訪れている。
3階の有料展示室では、海を舞台とした生命の進化が展示されており、大人でも難しい専門的な内容がある。触れられるナンタン隕石は大人1人の大きさで855キロ。こすると手に鉄のにおいがつき、リアルな質感をもって学ぶことができる。
生命の海科学館を満喫したら、近くの竹島水族館に寄るのもよい。最近リニューアルされたこぢんまりとした水族館だが、希少な深海生物や、魚の食べ方の展示もあり、ここでも命を考えることができる。
海のまちで命を感じる旅はいかがだろうか。
楽しい時こそ忘れない
-

上野 凌(うえの りょう)
公益財団法人日本ライフセービング協会スポーツ本部副本部長・2018環
海は本当に楽しいところである。波と風の音に揺られ、遥か遠くを見て、地球を感じることができる。自然を前に人間は本当にちっぽけな存在であることを感じさせられる。
海は楽しいところでありつつ、危険がある場所でもある。潮の流れや風や波の影響を大きく受ける。泳ぎに自信があっても、ひとたび入ると、逆らえない流れがあったりする。
今や、街中では安全が担保され、危険を感じずとも生きていけるが自然は変わらない。だからこそ、海や自然環境を前に、“自分の命を守る”意識を忘れてはならない。
海での不慮の事故はこの30年、一向に減っていない。海を訪れる人は減っているにもかかわらずである。危険に気を配り、身を守りつつ、楽しむ。ライフセービングで学んだその姿勢は、どこでも役立つ。
人はいつか命を失う。でもその場所は「海」であってはならない。溺水は“予防可能な死”。海が笑顔溢れる場所になるように今後も活動していきたい。
いのちと社会
-

福澤 涼子(ふくざわ りょうこ)
株式会社第一生命経済研究所ライフデザイン研究部副主任研究員・2020政メ修
“自ら命を絶つ”という個人の大きな決断には、属する社会の仕組みが大きく影響している。社会学の古典であるデュルケーム著『自殺論』を読んで、大学1年生の私は、まるでSFの世界のようだと思い、この本をきっかけに社会に興味を持つようになった。福澤諭吉は、「Society」のことを「社会」ではなく「人間交際」と訳したという。人のつながりによって生み出されるものこそが社会だといえる。
私の所属するライフデザイン研究部では、1人ひとりの生き方・暮らし方がより良い方向に進むよう、日々、調査研究や情報発信を行っている。なかでも私はシェアハウスなどで子育てや高齢期の生活を助け合うような暮らし方に関心が強い。家族ではない人たちがつながって、協力したり喧嘩したりを繰り返しながら生きていく。そこには確実に小さな社会がある。そのような社会が、いかに「いのち」の大事さを気づかせ、生活の質を高めるのか。さまざまな現象をつぶさに観察し、その意義を探究していきたいと考えている。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |


森 陽香(もり ようこ)