【その他】
【社中交歓】メロン
2024/06/21
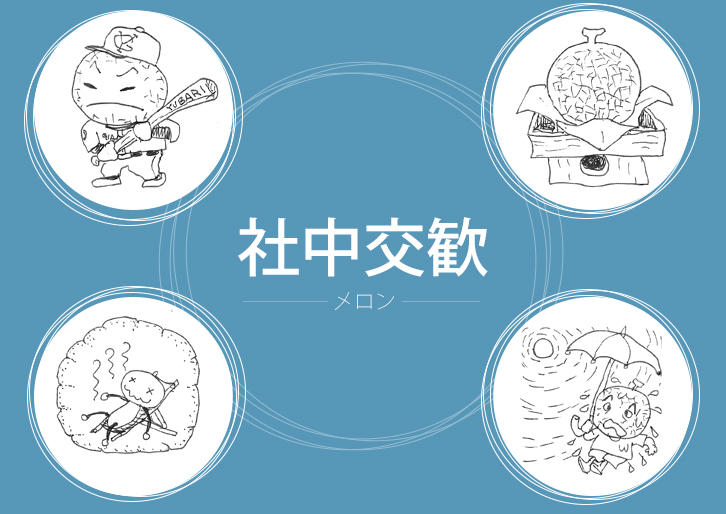
贈答品としてのメロン
アールスフェボリット種(Earl's favourite =ラドナー伯爵のお気に入り)メロンは19世紀末にイギリスで開発され、明治政府が日本をより豊かにしようと輸入し、新宿御苑内温室試験場で栽培が始まりました。品種改良を繰り返し、ジャコウの香りの濃厚な「マスクメロン」が誕生しました。明治後期には果実店に並び、大正時代には高品質で1年を通して収穫できるようになり、昭和時代にはその特徴から果物の王様と呼ばれ、フルーツギフトの代名詞となりました。
江戸市中では、果物を「水菓子」と呼んでいました。この語源からも果物は菓子の一類であり、野菜類とは違い、贈答品として重宝されるようになりました。日本には四季があり、人々の味覚も繊細で豊かなことから、品種改良を繰り返し、より美味しくそしてギフトとしての色や形の整った果実となります。贈答品としてのメロンが、他には無二の日本特有のフルーツギフト文化を創りだしたと言っても過言ではないのです。
ピンチをチャンスに変えた夕張メロン
-

高井 哲彦(たかい てつひこ)
北海道大学大学院経済学研究院准教授・1990経、92経修
夕張メロンは3つのピンチから生まれた挑戦の産物である。第一に北海道の寒さでは元々、甘くない加工用の赤肉メロンしか作れなかった。しかし、夕張農協はこれに静岡クラウンメロン系を掛け合わせ、高い糖度と独特な芳香を持つ赤肉マスクメロンを生み出した。
第二に夕張メロンは賞味期限が短いので空輸をせざるをえなかった。赤肉を「カボチャか?」と色物扱いされる中、長距離輸送に見合う箱入りの高級贈答品としてブランドを確立する必要があった。第三に夕張メロンが誕生したのは1961年。その後に夕張炭鉱が閉山し地域が縮小する中、火山灰質の山間地の逆境を克服し、ハウス栽培や蜜蜂交配、産地直送等の挑戦を重ねた。「黒いダイヤ」と呼ばれる石炭に代わり、夕張メロンは北海道を代表する「赤いダイヤ」となったのである。
現在では赤肉メロンは北海道の他地域でも栽培されるが、夕張メロン(品種名:夕張キング)の種子と品質は今でもJA夕張市が管理している。
美味しいメロンパンを作るコツ
-

池田 愛実(いけだ まなみ)
パン研究家、パン教室Crumb-クラム主宰・2011文
日本で老若男女に愛されているパンの代表といえばメロンパン。柔らかい菓子生地に、クッキーの生地を被せて、砂糖をまぶして格子模様をつける。これが意外と美味しく作るのが難しいのです。課題は2つ。
1つ目は、クッキー生地を被せて形作った後に1時間ほど温かいところで発酵させるのですが、クッキー生地にはバターがたくさん含まれているため、だれます。だれた生地は焼いてもなかなかサクッとしません。おすすめは発酵を低めの温度でとること。そうすると比較的サクッとした食感のメロンパンになります。
2つ目はパン生地の美味しさです。クッキー生地が美味しくできても、下のパンがパサパサでは美味しいメロンパンとは言えません。パンは「酵母菌」によって発酵しますが、市販の酵母菌であるドライイーストをたくさん入れると、短時間で発酵する一方で生地が急激に膨らみスカスカになりやすくなります。少ないイーストの量でゆっくり発酵させて、小麦粉にしっかり水を吸わせてあげるのが良いでしょう。
メロンにかけた夏
-
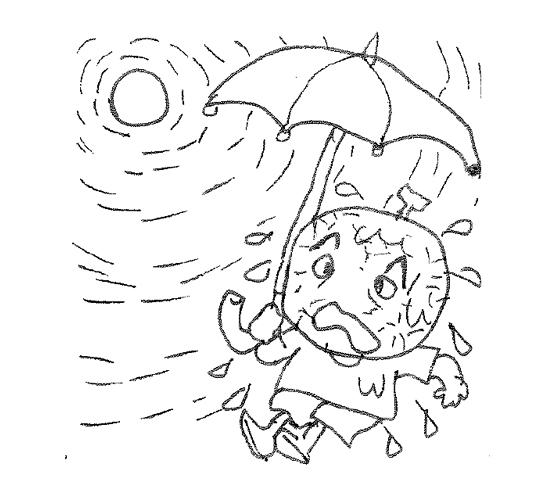
内藤 祥平(ないとう しょうへい)
株式会社日本農業代表取締役CEO・2015法
2019年の夏、タイ・チェンマイの炎天下で、日本品種の高品質メロン生産に挑んでいた。甘さと香りの高さが抜群で、ビジネスチャンスが大きいと考えたからだ。比較的涼しい山岳地帯とはいえ、太陽の照り返しは容赦なく、日々の疲れを癒すのは夕暮れ時のRegency(タイのブランデー)だけだった。
課題は山積みだった。地権者交渉に時間を要し、不十分な水や電気のインフラに悩まされた。さらに、日本と異なる気候での安定生産は難題。それでも、秋までに小規模なハウスを確保し生産実証を開始したとき、一筋の希望を感じた。
結果的に年内にプロジェクトを終了せざるを得なかった。市場にはすでに中品質のメロンが溢れ、私たちが目指した販売単価の実現は困難を極めた。計画の甘さと現地市場への理解不足を痛感した。
現在、新たな挑戦を続けている。同じチェンマイでイチゴの生産に取り組み、5年目を迎える。イチゴの生産も容易ではないが、続く大きな夢。未来への希望と挑戦を胸に、これからも歩み続ける。
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

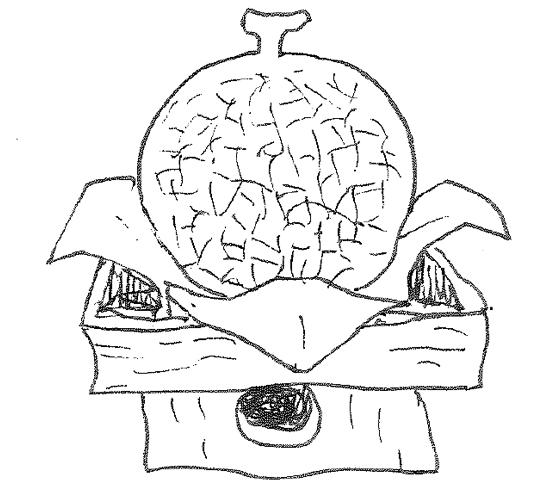
大島 博(おおしま ひろし)