【執筆ノート】
『「フランス文学」はいかに創られたか──敗北から国民文学の形成へ』
2026/01/19
今にして、何だか大仰なタイトルを付けたものだと思っている。内容としてはタイトルどおりなのだが、注を合わせて250ページほどの小ぶりな本である。
この本を執筆したきっかけは、旧知の編集者から「小倉先生とフランス文学の関わりを、個人史的に語るような本を書いてみませんか」と提案されたことだった。世間には、学者が自分の研究者人生を振りかえる回想録の類は少なくないが、私はあまり関心がない。
ただ、その編集者の言葉に考えさせられた。自分が大学で学んだフランス文学、その後教師になってから学生相手に講義をしてきたフランス文学は、そもそも本国でどのようにして成立したのか。換言すれば、フランス語で書かれた文学はいつから「フランス文学」になったのか。
これは国民文学の成立と関連する問題になる。国によって多少の違いはあるが、一般にヨーロッパでは18世紀末から19世紀末にかけて、国民文学が成立したとされる。政治的な統一体としての近代国民国家の誕生がその背景にある。日本でも「国文学」の概念が生まれたのは明治時代のことだ。
それに対して本書では、ベネディクト・アンダーソン流の国民国家論と距離を置いて、フランス文学の成立を思想史的、文化史的な観点から問いかけた。スタール夫人が『文学論』(1800年)において、国民の精神と習俗を表現する営みとして国民文学を提唱し、その後アンペールやタイヤンディエが文学史の基礎を築き、19世紀末にランソンが「フランス文学史」を確立した、というのが議論の大きな流れである。
とりわけ1871年、普仏戦争で喫した敗北は、フランス国民に教育制度を改革する必要性を強く感じさせた。その一環として、生徒や学生たちにフランス文学を学習させ、祖国の文化的偉業を自覚させることが重要とされたのだった。
ランソンが示したフランス文学史のモデルは、その後長い間にわたって規範となるが、21世紀の現在、文学史の書き換えが世界各国で進んでいる。日本で教えるフランス文学史も、その構成と内容を抜本的に見直す時期が来ていると感じる。
『「フランス文学」はいかに創られたか──敗北から国民文学の形成へ』
小倉 孝誠
白水社
250頁、2,750円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

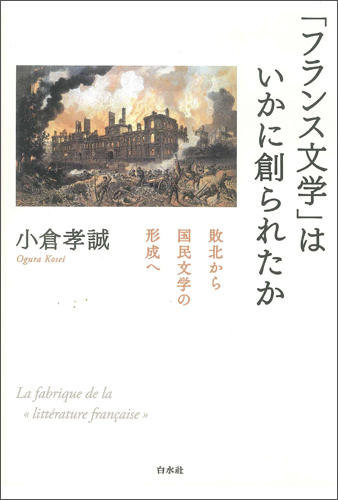
小倉 孝誠(おぐら こうせい)
慶應義塾大学教授