【執筆ノート】
『逆格差論、名護市長 岸本建男と象設計集団が遺したもの』
2025/11/11
けっして多くのことを知っているわけではないが、戦後日本社会の変貌を人々の「意識」のあり方から考えてみたいと思って何冊かの本を書いてきた。
2020年に『「象徴」のいる国で』で昭和・平成・令和の3人の天皇を論じた後、次はどうしても沖縄を書かなくてはならないと思った。
その後、「復帰」から50年目の年に『沖縄の岸辺へ──50年の感情史』を書いていて、今度の本の主人公たちのことを知った。
後に名護市長も務めた市役所職員の岸本建男と、"古代的アヴァンギャルド"とでも言うべき建築を数多くつくった象設計集団である。
両者はちょうど「復帰」の年に沖縄で出会った。複数の因縁があったから、まったくの偶然ではないが、今思えば「奇跡」の遭遇だった。
彼らは名護や今帰仁(なきじん)など沖縄北部を舞台に各々の発想を持ち寄り、画期的なまちづくり計画と類のない建築(名護市庁舎、今帰仁村中央公民館など)を生み出した。
それらの創造的な活動の「核」になったのが「逆格差論」である。
本土政府が経済的格差を是正するという触れ込みで押し付けた工業化/近代化路線に正面切って対抗しえた根拠は、本土よりずっと豊潤な自然環境と簡明な生活思想だった。第一次産業をベースに組み立てられた潔いほどシンプルな労働社会論は、急激に浸透しつつあった消費文化に異議を申し立てる「もう一つの沖縄」の姿と見えた。
後年、辺野古新基地建設をめぐって深刻な分断に苛まれる以前、名護のまちにこうした時代が(たとえ短い間でも)あったことが驚きだった。
今回の取材で、「逆格差論」の現場に立ち会った方々から、直接に貴重なお話をうかがうことができたのは何よりも幸せなことだった。
もちろん、その思想はまだ生きている。後の「内発的発展論」の先駆けであり、高度福祉社会の次を見る視点もある。広い意味で循環型社会の実験を試みたところもある。
そして何よりも重いのは、戦後日本社会をいまだに呪縛し続ける「豊かさと成長」の物語に、潔い反論を放ち続けていることである。

『逆格差論、名護市長 岸本建男と象設計集団が遺したもの』
菊地 史彦
論創社
320頁、2,750円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

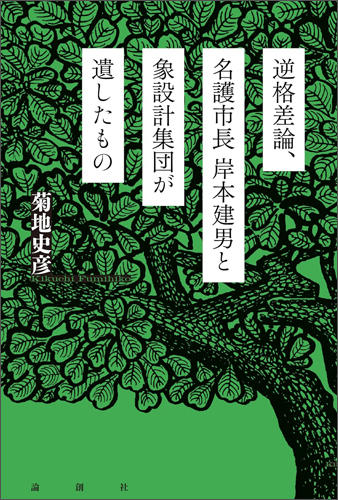
菊地 史彦(きくち ふみひこ)
戦後史研究者、文筆家・塾員