【執筆ノート】
『中華料理と日本人──帝国主義から懐かしの味への100年史』
2025/10/21
日本の西洋料理が明治期の文明開化から広まったのだとしたら、中華料理は20世紀前半の日本帝国の拡大とともに広まったといえるのか。また中華料理は、日本人にとって外国料理であるにもかかわらず、懐かしいと感じることがあるのはなぜなのか。本書では、料理がもつ精神的な側面に注目しながら、これらの疑問にどう答えられるのか考えた。
今私たちが食べている中華料理は、実はこの約100年間で広まったものがほとんどである。日本の中華料理は、チャイナタウンの華僑・華人が中心に広めたものと、おもに日本人が中国から伝えたものとがあるが、本書の前半で取り上げた肉まん、ジンギスカン、餃子などが後者の代表例である。
1910年代に肉まんが普及し始めたのは、西洋人に対する日本人の身体的な劣等感を克服するために、西洋の牛肉料理ではなく中国の豚肉料理が提唱されたことがきっかけであった(第1章)。ジンギスカンは、1910年頃に北京の日本人が羊肉の炙り焼きを「成吉思汗」と名づけ、それは1932年に建国された満洲国の名物料理になっただけでなく、その勇ましい名前から陸軍が戦意高揚の宣伝に用いることもあった(第2章)。焼き餃子は、日本人が敗戦後に満洲から伝えた「引揚者料理」であり、1950年代には「餃子時代」と呼ばれたほど急速に普及した。それは、引揚者たちを包容した戦後日本社会の国民再統合の象徴になりうる食べ物であった(第3章)。
日本の中華料理は、イギリスのカレーなどと同様に、帝国主義と深い関わりをもつ。だが、戦後にはノスタルジアの対象となり、地域振興に活用され、文化遺産にもなった。日本の中華料理は日中交流の産物であり、その明るい面も暗い面もあわせて世界史の一部としてとらえることで、その価値はいっそう高まると思う。
本書を読了してくれた叔父(塾員)の亡父は、関東軍の将校で、満洲で敗戦を迎えてシベリアに抑留された後に帰国した。彼は客のもてなしが好きで、前日からマトンを仕込んだジンギスカンを得意とし、叔父もそれが好物であったという。本書を自身の思い出と重ね合わせて読んでいただけてうれしかった。
『中華料理と日本人──帝国主義から懐かしの味への100年史』
岩間 一弘
中公新書
304頁、1,166円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

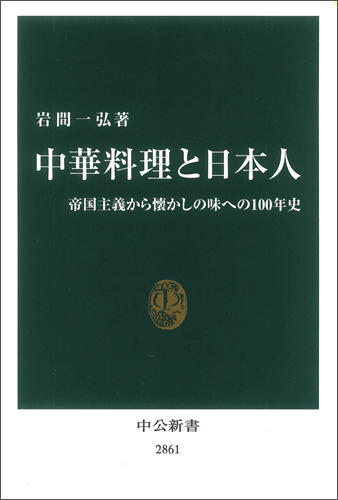
岩間 一弘(いわま かずひろ)
慶應義塾大学文学部教授