【執筆ノート】
『海底の覇権争奪──知られざる海底ケーブルの地政学』
2025/09/03
1990年代半ばにインターネットの商用化が始まった頃、「インターネットはアメリカのものだ」とよく言われた。正しくもあり、まちがってもいるとも思うが、いずれにしても、その前はどうだったのか気になって調べ始めた。
すると、19世紀には大英帝国が電信のネットワークを世界中に張り巡らせており、およそ3分の2を牛耳っていたことがわかった。最初の海底ケーブルが英仏間のドーバー海峡に敷設されたのは1851年で、慶應義塾創設の7年前である。
そこから海底ケーブルを探す旅が始まった。
海底に埋める技術が未熟だった時代の古いケーブルは、浅い海の海底で見ることができる。例えば、1902年にハワイに最初につながった海底ケーブルは、ワイキキ・ビーチ近くの海底にまだある。
しかし、現代の海底ケーブルは、漁網や錨で切られないようにかなり深いところに行かないと見られない。その代わり、私は海外出張の度に陸揚局と呼ばれる陸上の設備を探すようになった。文字通り、海底からケーブルを引き上げるための施設だ。
冷戦時代の陸揚局は、核兵器が落ちても生き残れるように地下化されていた。米国で見せてもらったその時代の陸揚局は軍の基地の中に作られていた。現代の陸揚局はもっと簡素で窓のない建物が多いが、安全保障上の理由から場所が秘密になっていることも多い。
大日本帝国の時代の陸揚庫もひっそりと各地に残っている。北海道の稚内の陸揚庫は樺太とつながり、根室の陸揚庫は北方領土とつながっていた。石垣島は台湾とつながっていた。海底ケーブルから見直す日本の近現代史はとてもおもしろい。
しかし、戦時には切られてしまうのが海底ケーブルだ。2つの大戦でもいくつかのケーブルは開戦とともに切られた。近年、バルト海や台湾近海でケーブル切断「事故」が相次いでいる。貨物船や漁船がケーブルを引っかけて切ってしまうのだが、本当に事故なのかは疑わしい。
日本のような島国にとっては、現代の国際通信の99パーセントは海底ケーブルを通る。情報社会の生命線と言って良いのが海底ケーブルだ。
『海底の覇権争奪──知られざる海底ケーブルの地政学』
土屋 大洋
日本経済新聞出版
284頁、2,860円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

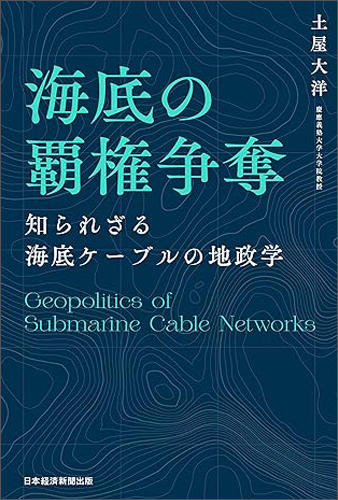
土屋 大洋(つちや もとひろ)
慶應義塾常任理事