【執筆ノート】
『メディアとしての福沢諭吉──表象・政治・朝鮮問題』
2025/07/28
10年以上前、サザエさんを見ていたら「父さんネギを買う」という話があった。波平が仕事帰りにネギを買ってくるよう頼まれて最初は激怒するが、その後買い物袋からネギを突き出して歩く姿を、カツオのクラスメイトの花沢さんが目撃して噂になる話だったと記憶する。そう、一昔前まで、威厳ある父がネギなど提げて帰ってはならなかったのだ。
これを見て、私はある回想を思い出した。慶応4年4月、入学するために慶應義塾を訪ねた荘田平五郎(後の三菱の大実業家)が、ちょうど外出から帰ってきた福澤諭吉と出くわして仰天する。町人風の頭髪に書生風の羽織、そしてネギを一束持っていたのだ。
福澤は極めて意識的にネギを買っている。身分相応とか、男たるもの、学校の先生たるもの、などという常識を軽蔑して一顧だにしない自分の姿を見せている。それが周囲を感化して、やがて自由や平等を日常に変えることを福澤は知っていた。
文章を書くときも福澤は「見られる自分」の意識から、その文章がいつ誰にどのように読まれるかを想定して書く。子供向けに書くことの難しさを知り、しかも子供を変えれば未来が変わることも知っている。だから学者たちが馬鹿にしても、たくさんの子供向けの本を書く。
新聞『時事新報』を読み解く上でも「見られる自分」の意識は重要だ。福澤は未来に大思想家として評価される論文のつもりで社説を書かない。その日の情勢下でその日の日本を少しでもプラスに転じる意図で書かれ、明日にはゴミになると考えている。
福澤は目指すべき理想を「文明主義」と呼ぶ。すべての「個」が独立して尊重され、コミュニケーションが最大限活性化した状態が「文明」であり、それに少しでも近づけようとしている。それを見定めれば、『時事新報』の一貫性が見えてくる。なぜ福澤が国会開設の年に、急に紙上で歌舞伎に熱を入れるのか、なぜ大災害時に義捐金に熱心なのか、なぜキリスト教排撃から容認に転じたか、そしてなぜ「脱亜論」を書いたのか。「メディアとして」とは、「見られる自分」を最大限活用して「文明主義」を目指した全く新しい福澤の読み解き方を意味しているのである。
『メディアとしての福沢諭吉──表象・政治・朝鮮問題』
都倉 武之
慶應義塾大学出版会
476頁、4,950円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

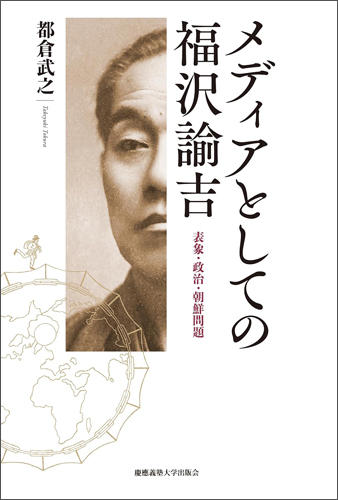
都倉 武之(とくら たけゆき)
慶應義塾福澤研究センター教授