【執筆ノート】
『立ち読みの歴史』
2025/07/16
4月に早川書房の「ハヤカワ新書」から『立ち読みの歴史』という本を出しました。
日本人なら誰でも当たり前と思っている書店での「立ち読み」。けれど、どうやらこの習俗は日本独自のものらしいと、昭和時代に洋行帰りがそう言うのです。一方で本屋に入って本をめくる、という動作は海外でも昔からあります。どういうこと?
NHK大河ドラマ「べらぼう」に本屋が出てきます。ところが江戸の本屋は「座売り」式で、立ち読みできません。すると、この日本で明治以降、いつか、どこかで「立ち読み」が始まったはず、と問題が立ちます。それを探ったのが拙著『立ち読みの歴史』。ぜひ書店へ足を運び、本書を立ち読みしてください。
しかし、誰もが自明視して気づかない日本人の習俗をなぜ私は意識化できたのでしょう。
1989年に塾の図書館(当時、三田情報センター)で夜間閲覧の学生嘱託をしました。そこで気づいたのが本の紛失問題。学士入学で入った図書館・情報学専攻で田村俊作先生の指導のもと卒論の素材にしましたが、その時に書店の万引き問題も先行文献がほとんどないことに気づきました。
ところで私の前職、レファレンス司書の技法に「同時に出るもの探索法」というワザがあります。ある事物を調べてなかなか文献が出ない場合、同時に発生する違う事物を検索する、という技法です。当初、書店万引き文献がなかなか見つからず、同時発生する別件は何か、ということで「立ち読み」に目をつけたのでした。
私はかつて西洋史を専攻していた時代から古本好きで、その頃、紀田順一郎さんの『古書街を歩く』を読んで書物研究に目覚めました。それから40年、4月に私が発行する『近代出版研究』で「書物百般・紀田順一郎の世界」という特集を組みました。荒俣宏さんが長大な文章を寄せてくれていますが、お二人とも塾員。そこで自分も塾の愛書趣味の末席に連なっていたのかもしれないな、と思います。故・武者小路信和先生に図書館5階で授業中、変わり絵本を見せてもらったのも懐かしい思い出です。
『立ち読みの歴史』
小林 昌樹
ハヤカワ新書
200頁、1,320円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

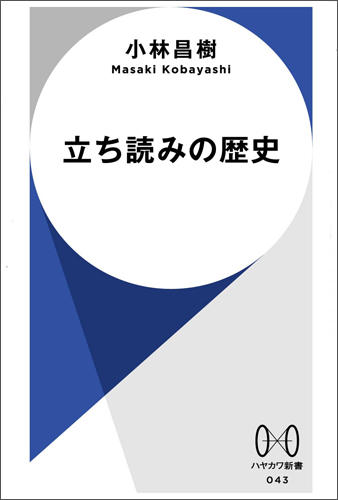
小林 昌樹(こばやし まさき)
近代出版研究所所長・塾員