【執筆ノート】
『皇室典範──明治の起草の攻防から現代の皇位継承問題まで』
2025/04/28
現行の皇室典範は、日本国憲法とともに1947年に制定された。それから80年近い歳月が流れ、その間に様々な制度的矛盾が指摘されながら、いまだ法改正に至っていない。
戦後の皇室典範が嫡出のみに皇位継承資格を認め、戦前の皇室典範を踏襲してなお「男系男子」を貫いたことは、皇位継承を不安定化させた。1990年代に入り、少子化が進むと、皇室も例外ではなく、皇族の減少が顕著になった。
そこで90年代後半、内閣官房、宮内庁、内閣法制局が赤坂プリンスホテルで極秘研究会を開催し、安定的皇位継承のための皇室典範改正のたたき台が密かに準備された。この原案は、2005年11月、小泉首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」の報告書に結実された。
その後も、皇位継承をめぐり様々な議論があったが、やはりこの報告書が重要な原点になっていることはまちがいない。報告書は直ちに法案化され通常国会への提出が予定された。しかしその矢先、秋篠宮紀子妃の懐妊が報じられ、いったん議論は棚上げされることになった。
同年9月に悠仁親王の誕生により、世間ではまるで問題が解決したかのように、議論は鎮静化した。しかし果たして、現在の徳仁天皇と秋篠宮の次の世代に1人の男子が誕生したからと言って、皇位継承は安定化したと言えるのであろうか。
比較的若い皇族は、悠仁親王を除けば、みな女子である。女性皇族は婚姻に伴い、いずれ皇室を去ることが想定される。果たして将来、悠仁親王を支える皇族は確保しうるであろうか。本書は改めて矛盾を抱える皇室典範について、明治の起草をめぐる攻防から、戦後憲法の一下位法になった現行皇室典範の成立過程を検証し、いまなお解決をみない皇位継承問題の政治的背景を明らかにする。
小泉内閣についで野田内閣、安倍内閣、そして菅内閣がこの問題にアプローチしたが、依然として解決の糸口を見出せずにいる。問題解決には、制度設計とともに手順研究が重要である。当初から、同問題をめぐっては「男系男子」を墨守する自民党内保守派が問題解決を阻んできた。
本書では、賢明な妥協を辞さない「最大公約数」が追求されている。
『皇室典範──明治の起草の攻防から現代の皇位継承問題まで』
笠原 英彦
中公新書
256頁、990円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

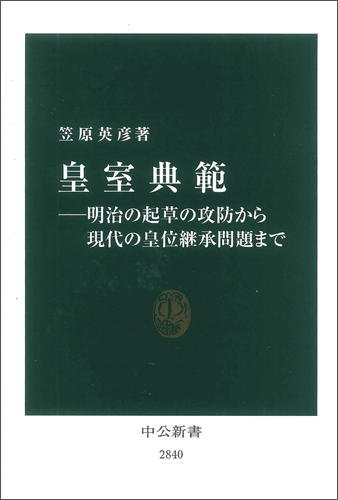
笠原 英彦(かさはら ひでひこ)
慶應義塾大学名誉教授