【執筆ノート】
『震災アーカイブを訪ねる──3・11現在進行形の歴史って?』
2025/04/14
3歳、3歳、1歳。2011年に起きた東日本大震災当時、我が家は乳幼児3人を抱えていた。東京電力福島第一原発の事故もあり、粉ミルクや飲料水、紙おむつが品薄に。妻子は一時、関西に身を寄せた。
同年秋には、故郷の福島県いわき市から横浜市内に避難していた祖母が99歳で世を去った。震災関連死とされ、毎年3月発表の数字に加えられて追悼の対象となっている。
買いだめや買い控え。計画停電や自主避難。直接の被害はなくても、身の回りに起きた生々しい同時代の出来事を記憶する人は多いだろう。
ただ、多くの人が体験・記憶し、世の関心を集めた出来事も時の流れには抗しがたい。記憶は薄れ、記憶がない世代、体験していない世代も増える。年々遠ざかる震災を今後、だれがどう伝えるのか。
一般論ではない。春に高校3年になる上の子たちは今も地震の揺れや祖母の姿を記憶する。一方、春から高校に進む下の子は記憶がない。自分は、この子たちに震災を「我が家の出来事」として語り継げるのか。
14年に雑誌の編集者から新聞記者に「社内転職」。18年から東京勤務に戻り被災地との距離が近づいた。震災10年を控えたコロナ禍の頃から恐る恐る被災地をドライブし始めた。最初は1人で。次いで家族や知人を連れて。いわき市内の津波被災地へ。北上し、双葉郡や相馬郡へ。宮城・岩手の沿岸部へ。
各地で交通網が整い、震災の遺構や公共施設ができ始めていた。福島県内は14年に国道6号が全線復旧し、車が通れるように(22年に自転車や徒歩でもOKに)。15年には常磐道が全線開業。16年の同県公式ポスター「来て。」にも背中を押された。20年にはJR常磐線全線が運行を再開。被災地は訪れにくい場所ではなくなっていた。
家族の物語をどう語り継ぐか。現在進行形の同時代史をどう見聞し、記録するか。2つの問いを抱えた旅を続けながら、中高生など10代の若い読者向けに被災地への旅を呼びかける本が生まれた。
単なる観光や勉強の場ではない。忘れてしまうのはもったいない。被災地は人生をかけて向き合う価値がある深い学びの場だと感じている。
『震災アーカイブを訪ねる──3・11現在進行形の歴史って?』
大内 悟史
ちくまQブックス
128頁、1,340円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

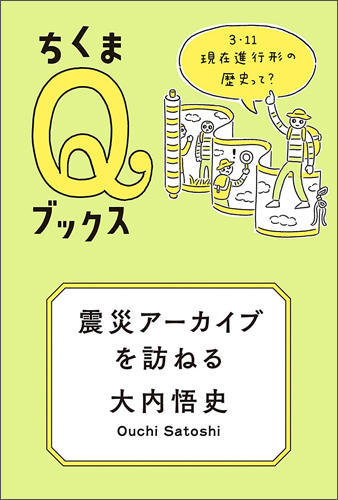
大内 悟史(おおうち さとし)
朝日新聞記者・塾員