【執筆ノート】
『立ち退かされるのは誰か?──ジェントリフィケーションと脅かされるコミュニティ』
2025/03/10
日々の生活の中で「街がきれいになった」と感じたことはあるだろうか。近年、都市のいろいろな場所で再開発、駅前整備が進められている。一般的に、こうした再開発は、利便性が向上した、街の雰囲気が明るくなった、と評価されることも多い。一方で、長くその地域で経営を続けてきた個人商店が店をたたみ、跡地がチェーン店やより価格帯の高い店に変わったという経験を持つ人もいるだろう。
都市はハード(建物等)の面でも、ソフト(社会)の面でも、常に変化し続けている。そうした中でしばし立ち止まり、再開発による変化が社会にどのような影響を及ぼしてきたのかを考える際、「ジェントリフィケーション」という言葉は一つの手がかりを与えてくれる。
ジェントリフィケーションとは、一般に、インナーエリアと呼ばれる都市中心部の労働者住宅地域、低所得地域が再開発され、そこに高級住宅や中流層以上を対象とする商業施設が新たに開業することで、住民の入れ替わりが起き、より高所得の住民が増加する現象を指す。本書はこの言葉をつくった英国の社会学者ルース・グラスの足跡を振り返ると同時に、カナダ・バンクーバーと横浜の低所得地域を取り上げ、現代の都市でジェントリフィケーションがどのような問題として生じているかを検討した。
日本ではこれまでジェントリフィケーションという言葉は一般にはさほど知られてはこなかった。しかし、都市での住宅不足、住宅価格・家賃高騰が社会問題となっている欧米社会では、ジェントリフィケーションは社会的により脆弱な層の立ち退き、追い出しにつながると理解されている。
翻って日本の都市ではどのようにジェントリフィケーションを考えればいいだろうか。現時点では、都市の同じ光景を見てもそれをジェントリフィケーションとみなす人もいればそうではない人もいる。目の前で生じている現象を呼び表す言葉を得ることで、人はそれを「理解する」ことができる。都市・地域の変化について考える際、ジェントリフィケーションは今後よりいっそう重要な言葉となっていくに違いない。
『立ち退かされるのは誰か?──ジェントリフィケーションと脅かされるコミュニティ』
山本 薫子
慶應義塾大学出版会
288頁、2,970円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

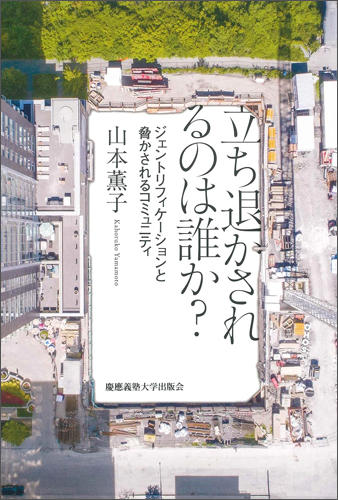
山本 薫子(やまもと かほるこ)
東京都立大学都市環境学部准教授・塾員