【執筆ノート】
『教員不足──誰が子どもを支えるのか』
2025/02/25
「今日がまだ木曜日であることに絶望しています」。本書は、ある中学校の先生のこんな言葉から始まる。
常識的に考えれば、少子化が急激に進み、教員需要も激減したはずなのに、なぜ学校はこんなに過酷な教員不足になってしまったのか?
この問いに答えるために、そもそも教員不足とはいったい何のどのような状態なのか、どのようにして教員不足が引き起こされてきたのか、その全体像を明らかにしたのが本書である。手がかりにしたのは、ある自治体を対象に、独自に実施した調査データである。
この調査によって、教員不足はおよそ4段階を経て進行してきたこと、そして不足を引き起こした複合的な要因の中でも、各地方自治体が少子化を睨んで正規雇用教員の数を採用控えしすぎたことが、最大の要因と考えられることが明らかになった。その背景には、2000年代に進行した国の行財政改革があった。
いったいどうすればよいのか。10年前なら教員採用数を増やせば対応できたはずだったが、もはや志望者も減って採用数を簡単に増やせない悪循環に陥っている。そこで本書では、私なりの政策提言をおこなうと共に、教員不足が放置されたらどうなってしまうのかを、アメリカの状況を手がかりに考察した。
アメリカでは教員免許制度を緩和しても不足は改善せず、軍人や移民を教壇に立たせる州も増えている。貧しい地域に生まれた子どもは、まともな教育が受けられなくなり、一生貧困から抜け出せず、社会の分断が進む。ミドル・クラスは、重い学費負担にあえぎながら子どもを私立学校に行かせるが、その学費は高騰するばかりだ。つまり教員不足は、単なる教育問題に留まらず、これからの日本社会のあり方の根幹にかかわる問題なのである。
「タイムリーな出版ですね」とお祝いの言葉をいただくが、正直なところ私の胸中は複雑だ。本来なら、もっと早くに問題が解決され、本書の刊行など不要であってほしかった。しかし、今ならまだ間に合うかもしれない。一人でも多くの方に本書を手にとっていただき、これからの日本をどうしていくのか、一緒に考えていただければ有り難い。
『教員不足──誰が子どもを支えるのか』
佐久間 亜紀
岩波新書
256頁、1,056円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

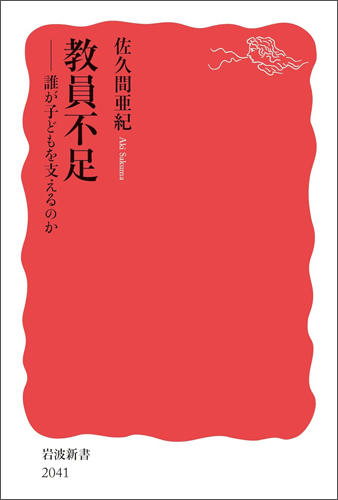
佐久間 亜紀(さくま あき)
慶應義塾大学教職課程センター教授