【執筆ノート】
『在野と独学の近代─ダーウィン、マルクスから南方熊楠、牧野富太郎まで』
2025/01/17
昨今、大学の学問は危機を迎えつつある。大学の研究者という職業が、若者にとって魅力的でなくなったのが最大の原因だろう(安定したポストを得るまでに時間がかかること、かつてよりずっと忙しくなったことなど)。一方で、ネットの発達もあり、在野での研究は進捗著しい。ふつうに就職して仕事をしながら、趣味として学問にとりくむひとたちの活躍がめだってきている。しかし、もったいないことに、現代の日本では両者が分断されており、大学の研究者(プロ)と、在野のアマチュアが同じ場で対等に協力しあうのは、非常に難しい。それにしても、こうした状況は、いつどのようにして生じたのか。
私は博物学者の南方熊楠をずっと扱ってきたこともあり、この問題がずっと気になっていた。熊楠は遊学先のロンドンで研究生活に入り、大英博物館などで仕事をしたが、あくまでもアマチュアとしてであった。それでいて、一人前の研究者として認められていた。ところが、1900年に帰国した熊楠はギャップに苦しめられる。明治の日本には、東大という官学があり、民間とはきっぱり分けられていたのであった。
実はここに謎を解く手がかりのひとつがある。東大は政府のつくった学校だったから、当然のように官の側にある。それに対して、イギリスのオクスフォード大学やケンブリッジ大学は民間で発生した機関であり、国立大学ではない。そのため、政府の御用機関といった側面も薄い。
日本でも、プロとアマチュアが協力してうまくいった例がある。牧野富太郎は東大で講師を務めながら、各地の植物愛好家たちとつながることで、日本全国の植物情報を図鑑にまとめられた。高級官僚だった柳田国男は、民俗に関心のあるひとたちを動員して、習俗や昔話を集めた。熊楠は牧野とも柳田とも関わった。
プロとアマチュアの関係は両国で差異があり、イギリスはヨコ型、日本ではタテ型であったといった特徴をもつ。社会における学問の位置付けからは、その国のことが透けて見える。
本書が、大学と民間とを問わず、多くのひとたちが学問を楽しみ、科学の発展に貢献できるような学術空間のヒントになれば、と思っている。
『在野と独学の近代─ダーウィン、マルクスから南方熊楠、牧野富太郎まで』
志村 真幸
中公新書
288頁、1,056円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

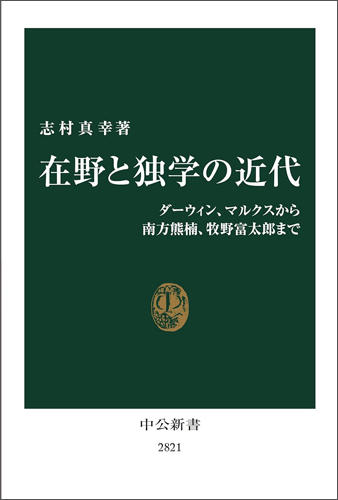
志村 真幸(しむら まさき)
慶應義塾大学文学部准教授