【執筆ノート】
『歴史学はこう考える』
2024/12/24
歴史学の入門書や、その方法論に関する書物は少なくない。そのなかで本書の特徴を挙げるとすれば、歴史家の著作の実例に即して、歴史家は「何をしているのか」についての説明を試みた点にあるだろう。
たとえば、歴史家は論文のなかで、史料を引用し、そこから読み取った情報を現在の読者に対して説明する。このとき、歴史家の書く文章の時制はどうなるだろうか。子細に見ると、案外、歴史家は現在時制を使っている。「……であることがわかる」とか「……であることが見てとれる」といった具合である。歴史家は、常に過去時制で過去について語っているわけではなく、「いまここにこういう史料がありますね、ここからこういうことが読み取れますね」というモード、つまりあるテクストを読者と共有しながら話を進めるやり方で論文を書いているのである。
ところで、直接の関係はないのだが、ちょうどこの本の執筆期間と並行して、私は短歌を作り始めた。短歌の制作の上で重視されるのが「歌会」という場である(歌人みんなが歌会好きというわけではないが)。歌会では1つの歌について、数分から数十分という単位で複数の人がコメント(評)を述べる。初めて歌会に参加したときにすぐに気が付いたのは「これは歴史家が史料を見てゆくときの手つきに似ている」ということだった。短歌の言葉は詩の言葉だから、短歌の組み立てられ方は日常の言葉の運用法とは違うのだけれど、だからといって歌に書かれている言葉と無関係に評をしても良いというわけではない。つまり、評は何らかの形で1首の歌のなかに根拠を持っていなければならない。日常言語とは異なる言葉の運用がなされているとしても、それがどのように異なっているのかについて、歌会参加者たちは1首の歌を共有した上で考える。
なぜこんなことを書いているかというと、本書で試みた作業は、歴史家や歴史に興味がない方にも面白がってもらえるかもしれない、と思ったからである。ある言葉を共有した上で何かを述べる機会は私たちの生活の至るところにあるのだし、その適切な遂行は、まともに(あるいは、楽しく)言葉を交わしあうことにつながってもいるだろう。
『歴史学はこう考える』
松沢 裕作
ちくま新書
288頁、1,034円(税込)
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

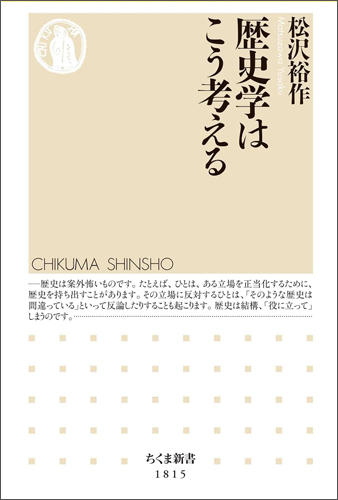
松沢 裕作(まつざわ ゆうさく)
慶應義塾大学経済学部教授