【執筆ノート】
『NPOとは何か──災害ボランティア、地域の居場所から気候変動対策まで』
2024/10/25
「慶應義塾だってNPOだよね」と授業で話すと、学生は皆きょとんとする。多くの人が思い描きがちな「NPOのイメージ」と重ならないからだろう。しかし、NPOという存在が、政府とは独立に、志のある人たちが自発的に結社し、ともに協力し社会のために活動する組織だとすれば、慶應義塾の成り立ちはまさにそれであった。そして、多くのNPOを生み出してきた存在でもある。
NPOと名付けられるずっと以前より、私たちの社会にはこうした民間・非営利の公益的な活動がある。行政では対応が難しく、営利活動にも馴染まない分野に強みがあり、家族や地域などの中間集団が細るのと入れ替わるように存在感を増してきた。実は、想像以上に多様な存在で、ボランティアが記事作成するウィキペディアも米国のNPOが運営する。
日本では、1995年に阪神・淡路大震災における「ボランティア元年」があり、世の関心をNPOに向けさせる契機ともなった。NPO法人はこの流れで誕生したもので、その数は現在5万弱ほど。いまや法人形態も多様化し、計10万ある社団・財団法人のなかにも公益的な活動を行うものが多く、必ずしもNPO=NPO法人というわけでもない。社会において普遍的な存在だが、制度的な意味でのNPOは国や時代によって移り変わる。
もっとも、多様で複雑な存在は、わかりづらく、それ故先入観で見られがちで、人びとのイメージと実際のNPOはときに大きく乖離する。とくに、「非営利」の語から、どこか自己犠牲的なものに映る(したがって偽善的との印象を呼び込みやすい)が、ここでいう非営利とは、利潤を最大化し利害関係者への分配が目的でないという意味で、すべて無償や無報酬だというのも誤解である。
問題ある組織も当然あるが、その1事例をもってNPO全体が印象で語られがちでもある。信頼される政府やそうでない政府、人気企業やブラック企業があるのと同様なのだが、こうしたことも、未だ十分な理解に至っていないから起こるのだろう。
慶應義塾がそうであるように、社会に欠かせない組織となるものもきっと多くある。本書が、少しでもその世界の理解の助けになれば嬉しい。
『NPOとは何か──災害ボランティア、地域の居場所から気候変動対策まで』
宮垣 元
中公新書
288頁、1,078円(税込)
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

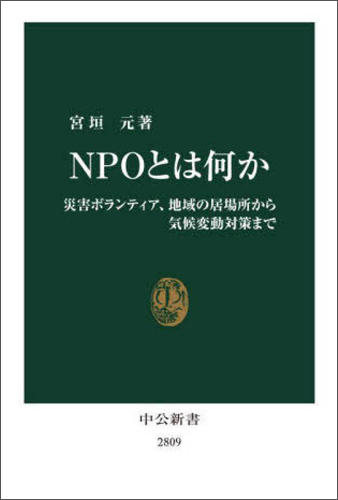
宮垣 元(みやがき げ ん)
慶應義塾大学総合政策学部教授