【執筆ノート】
『核のプロパガンダ──「原子力」はどのように展示されてきたか』
2024/05/22
各地に建てられた原発PR施設、原爆の災禍を今に伝える広島や長崎の記念館、被爆した船体をそのまま保存した第五福竜丸展示館、「原爆の図」を展示した丸木美術館など、全国各地には原子力をテーマとした様々な施設があります。本書はそうした施設の展示を紹介し、核の戦後社会史を考察するために書かれました。
私の専門は美術やデザインであり、原子力に積極的に関与する立場ではありません。そんな人間がなぜこの本を書いたかというと、ここ10年来取り組んできた万博研究や博物館研究の道程で原子力というテーマと遭遇したからです。課題解決を前面に押し出した近年の万博ではSDGsや再生エネルギーがしばしばクローズアップされますが、かつては原子力をテーマとした展示も盛んに試みられていました。1970年の大阪万博のシンボルである岡本太郎の「太陽の塔」も、実は原子力と深い関わりがあります。一方、資料や作品の収集・展示施設である博物館も、近年は社会への貢献を求められることが多くなり、国際的な統括組織であるICOM(国際博物館会議)は2022年のプラハ総会で新しい定義を採択しましたが、多様性と持続可能性を新たなミッションとして掲げたその定義は、原子力の展示施設についての再考を促すものでした。
原子力に関する本は数多く出版されていますが、私には科学者や市民運動家が書くような本は書けないし、そもそも書く理由がありません。ですが展示という観点から原子力を論じれば新たな問題提起ができるのではないか。私に本書を書かせたのは、類書の乏しい本、誰も書いたことのない本を書いてみたいという野心だったのかもしれません。
映画『オッペンハイマー』はマンハッタン計画で人類史上初の原爆開発に成功した天才科学者の足跡と苦悩を描いた傑作ですが、本書では、ほぼ同時期に日本でも原爆開発が計画されていたものの実現しなかった経緯を詳述し、合わせてそのプロセスを展覧会とする架空の展示構想を披露しています。センシティブな問題ですが、読者を不快にさせない最低限の配慮をしたうえでなら、このような思考実験を展開する機会があってもよいのではないでしょうか。
『核のプロパガンダ──「原子力」はどのように展示されてきたか』
暮沢剛巳
平凡社
368頁、3,740円〈税込〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

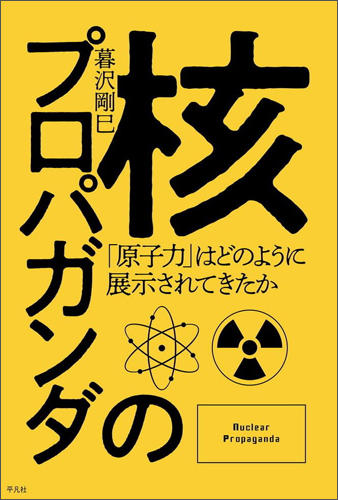
暮沢 剛巳(くれさわ たけみ)
東京工科大学デザイン学部教授・塾員