【執筆ノート】
『木地屋幻想──紀伊の森の漂泊民』
2020/10/16
定年後、生まれ育った東京を離れ、奈良県明日香村を経て三重県熊野市に移住した。傾斜地に建つ借家の窓から熊野灘を眺める暮らしも10年になる。そこで古代史を探究してきたが、今回初めて近世に分け入った。
紀伊国(きのくに)は「木の国」でもある。森の奥には木地屋(きじや)(木地師)やサンカがいた。前者はトチ・ブナ・ケヤキ・ミズメなどを刳(く)り抜いて椀や盆、杓子などを作る職人。後者は農具の箕みを編んだり、川魚を里人に売ったりした。そんな山の漂泊民はもういないから、古老の切れ切れの記憶や墓石や過去帳などに、その痕跡や残り香を求めるしかない。
里人は山にあこがれ、森の漂泊の民にロマンを抱いてきた。私もその一人だ。熊野市歴史民俗資料館が「木地師 その伝承としごと」展を企画したのを機に、彼らの幻影を追い、関係者へのインタビューを重ねた。
全国で活動した木地屋たちは小椋谷(おぐらだに)(滋賀県東近江市の蛭谷(ひるたに)と君ケ畑(きみがはた)を心のふるさととし、平安時代の悲劇の主人公・惟喬(これたか)親王を祖神と崇める「共同幻想」の世界に生きた。私の取材は鈴鹿山脈の山懐・小椋谷で今も轆轤(ろくろ)を回している小椋昭二さんの訪問から始まった。「小椋」は木地屋特有の姓である。
山の漂泊民を見る里人の眼差しには好奇心も混じっていた。そこから「木地屋の娘には美人が多い」という俗説が生じ、それを里謡(りよう)がはやした。熊野市の奥山には「傾城(けいせい)(美人)木屋(こや)」という地名も残る。
山間に暮らす木地屋には色白の娘がいただろう。実際美女がいたかもしれない。だが好奇心が高じて「他所との交流が少ないから近親婚が多く、畜生谷の地名ともなった」となると放ってはおけない。確かに木地屋たちと里人との婚姻は少なかったようだが、良木を求めて各地を移動した彼らには仲間内の交流があり、そこで男女が結ばれる例も少なくなかったろう。好奇心が偏見、そして差別につながりかねない危険がそこにもある。
拙著には「木地屋の末裔が先祖の屋敷跡を発見する話」「とある木地屋の妻の墓からたどる一族の物語」など現地を踏んだ話を盛り込み、実際に訪ねてみようという読者のために写真や地図も多く使った。
『木地屋幻想──紀伊の森の漂泊民』
桐村 英一郎
七月社
168頁、2,000円〈税抜〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

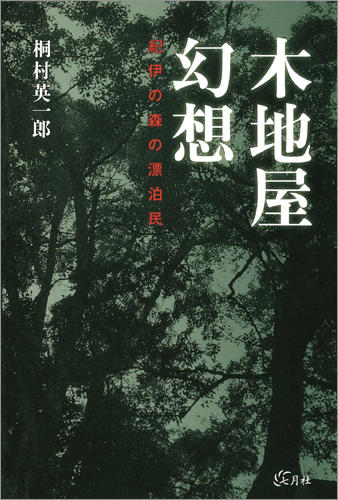
桐村 英一郎(きりむら えいいちろう)
元朝日新聞記者・塾員