【執筆ノート】
『市民の義務としての〈反乱〉──イギリス政治思想史におけるシティズンシップ論の系譜』
2020/09/07
「歴史ブーム」なるものが喧伝されて久しい。本の売れないこの時代にあって、歴史関連の書籍がたびたびベストセラーの名に上る。しかし一方で、教育の場では歴史系科目の内容の縮減、あるいは必履修科目からの除外を目指す動きが根強く見られる。一見相反するかに見える両者の現象は、実のところまったく首尾一貫している。すなわち、歴史は「趣味」としての地位に留まるべきものなのである。なぜ現代よりも劣った時代である古代や中世のことをわざわざ学ぶ必要があるのか。ウィッグ史観から「歴史の終焉」テーゼに至るまで、リベラルはこのような歴史観を理論の面で下支えし、一般民衆に流布してきた。
また、この国では「批判」が忌避される。「野党=批判=反日」という陳腐な方程式が多くの人々の心をとらえている。しかしながら、19世紀のイギリスにおいて、国を愛すればこそ批判が必要であることを主張した思想家がいた。本書の出発点であるT・H・グリーンである。「忠実な臣民」による盲従は国家を滅ぼす。対して国家を発展させようとする「知的愛国者」は「抵抗の義務」を有する。古代ローマを念頭に置いたこのような議論は、本書の表紙となっているカムッチーニ作「カエサルの死」の中でカエサルを囲む共和派議員たちの姿に象徴されている。
本書後半に登場するハロルド・ラスキは、グリーンやホブハウスといった思想的先達から多くのものを受け取った。では彼らを分かつものは何か。それはラスキの歴史観である。現代を無条件に賛美する歴史観は「思慮なき服従」につながる。市民であり続けるためには、歴史的な視点から現代という時代を絶えず相対化しなければならない。歴史とは人間という有限な存在による選択の連続である。その選択の中には正しかったものもあれば誤っていたものもあるだろう。そして誤りは正さなければならない。「反乱の義務」こそが市民であり続けること(シティズンシップ)の保証となるのである。
本書の執筆に要した10年という歳月は、筆者にとっては決して短いものではなかった。私が歴史に捧げた10年間の成果が、1人でも多くの読者に届くことを祈っている。
『市民の義務としての〈反乱〉──イギリス政治思想史におけるシティズンシップ論の系譜』
梅澤 佑介
慶應義塾大学出版会
344頁、3,200円〈税抜〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

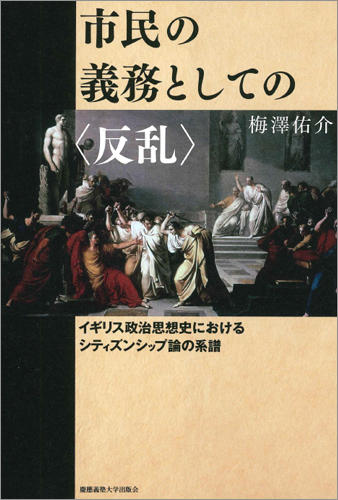
梅澤 佑介 (うめざわ ゆうすけ)
慶應義塾大学法学部非常勤講師・塾員