【執筆ノート】
『映画ノベライゼーションの世界──スクリーンから小説へ』
2020/05/19
こんな映画のワンシーンを想像して欲しい。場所は、近未来なデザインの高層ビル。その屋上で、敵に追い詰められたヒロインは、もはやこれまでとばかりに目を閉じ、背中から虚空へとその身をゆだねる――。
こうした情景を「映画化」するには、たとえば追い詰められたヒロインを上空から映すロングショットや、ビルの縁ぎりぎりに踏みとどまる彼女の足のクローズアップなど、映画特有の視点が必要となるだろう。では、ふたたびこれを「小説化」する場合、作家は何をすべきだろうか。
文学作品の映像化という現象については、これまで多くの学問的関心が寄せられ、膨大な研究書が刊行されてきたけれど、こと、映像作品の小説化――すなわち「ノベライゼーション」という営みについての研究は、国内外でも数えるほどしかなされてこなかった。前著『映画原作派のためのアダプテーション入門』にて、アメリカ文学の「映画化」を論じた私は、それから2年の歳月を費やし、主にアメリカ映画の「小説化」についてのリサーチを行った。明らかになったのは、冒頭のような映像表現を文章化するとき、意外にも多くのノベライゼーション作品は、視覚的描写を避ける傾向にあるということだった。
映像的臨場感の再現よりも、事実として何が起こり、ヒロインは何を考えているかに集中すること。何しろ、ノベライゼーションの執筆は初稿段階の脚本をもとに始められ、撮影現場の進行とは無関係に、映画公開前の刊行を目指すのだ。重要視されるのは、いかに製作陣のイメージを崩さずに、宣伝となる「語り」を構築できるかであって、作家たちに、まだ見ぬ映像を勝手に創作するといった越権行為は許されない。商業映画の発展に深く関わりながらも、彼らはみな、時間的にも経済的にも、想像を絶する制約のなかで孤軍奮闘を続けてきたのである。
映画がまだ、連続活劇と呼ばれていた頃から、CGが当たり前になりその映像表現に限界がなくなりつつある現代まで、映画史とともに密かな発展をし続けてきた映画ノベライゼーションの世界。活字文化の古くて新しい一面を、本書を通じて楽しんでいただけたらと思う。
『映画ノベライゼーションの世界──スクリーンから小説へ』
波戸岡 景太
小鳥遊書房
200頁、2,000円〈税抜〉
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

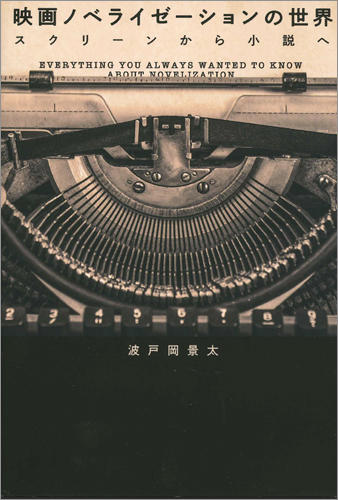
波戸岡 景太(はとおか けいた)
明治大学教授・塾員