【執筆ノート】
『「笑い」の解剖──経済学者が解く50の疑問』
2019/12/17
笑いは身近な感情表現だが、いざ何かと問われると答えるのが難しい。これまで多くの哲学者や心理学者がその謎を解明すべく格闘してきた。曰く、笑いとは、優位に立つこと、機械的なこわばり、鬱積した心的エネルギーの放出、予想と現実の不一致等々。どれも笑いの一面を説明するものの完全ではない。なぞかけは誰も見下さず、こわばってもいない。ダジャレはエネルギーの放出ほど大袈裟でなく、乗り物酔いは予想と現実の不一致から生じるが笑えない。
落語やお笑いは以前から好きだったので、いつか笑いを研究したいと思っていた。そのきっかけは、NHK Eテレ『オイコノミア』での又吉直樹氏との共演である。同氏からお笑いの世界について直接話を聞けたことで、この未知の世界に足を踏み入れようという気になった。
笑いの源泉は世の中の不自然さにある。それに対して、無視もせず、解決しようともせず腹も立てないのが笑いだ。いったんアタマで受け入れ、咀嚼し、最後に心を解放しているのである。だが、誰もがいつでも笑えるわけではない。そこに至るまでには何らかの条件があるはずだ。心理学、脳科学、臨床心理の先生方から多くのヒントをいただき、思索をめぐらせた結果、辿り着いたのが「不自然さをもたらした主体への親しみ」と「不自然さに対する非当事者性」という2つの条件だった。親しみがあるため受け入れはするものの、非当事者性ゆえに深く関わらず心の解放ができる。こうして不自然さの発見/創作から心の解放に至るまでの「四段階説」が完成した。
この四段階をクリアするハードルは、私たちを取り巻く環境や自らの脳の状態により、高くなったり低くなったりする。これが笑いの多様性だ。笑いのビジネスは、このハードルを効率的に下げるための技を開発する競争だと解釈できる。
笑いという機能が退化しなかったことも納得がいく。脳の働きを進化させ、高度な社会性を身につけた人類は、同時に人間特有のストレスと対峙せざるを得なくなった。不自然さから心を解放する笑いはこうした人類にとって不可欠なものになったのだ。現代を生きる私たちは笑いをもっと活用すべきなのである。
『「笑い」の解剖──経済学者が解く50の疑問』
中島 隆信
慶應義塾大学出版会
212頁、1,800円(税抜)
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

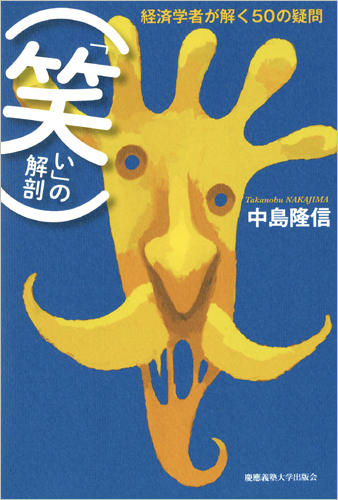
中島 隆信(なかじま たかのぶ)
慶應義塾大学商学部教授