【執筆ノート】
『大岡昇平の時代』
2019/12/09
大学時代からの親しい友人にこの本を贈ったら、礼状をもらった。
「若い頃、君がいちばん多くを語っていた作家を論じた本を、この年になって書いたことに、まずもって感慨があった」という趣旨のことがそこに記されていた。
私は、学生時代にあまり文学を論じたことなどなかったと自分では思っている。いわれてみて、そうだったのかなあと、それこそ感慨にひたったのだった。
高校時代に、『野火』や『武蔵野夫人』などの小説、さらには稀有な体験談である『俘虜記』などを読んだのが始まりで、何よりも日本の近・現代文学には見かけない、正確でしかもしなやかな文体に心惹かれた。
そのみごとな文章のせいであろうか、前にあげたような作品に『花影』や『事件』などを加えて、今、大岡作品は「昭和の古典」あつかいされている。そして皮肉なことに、古典にまつりあげられて、人びとがほとんど読まなくなっている。
しかし、私にとっては、今に至るまで「今日の」文学なのである。
私は出版社に勤めていた時代に、大岡作品を発表と同時代的に読むようになったのだが、大岡作品は常に最先端の文学のあり方を示していた。富永太郎や中原中也の伝記、自叙伝の試み、現代日本文学への不満を語る評論、その延長にある痛烈な論争と、大岡昇平はまことに生き生きと、多彩な仕事を展開した。
仕事のひろがりにとても追いつけない、と思いながら、それでも追いつづけるのをやめなかったのは、大岡の作品には、現代日本の文学がひきつがなければならないテーマが、つねに内在していたからだと思う。
たとえば『常識的文学論』(1962年刊)という評論集では、日本のエンタテイメント系小説の洪水が論じられているが、これは2000年代に入ってはさらに複雑な姿となって、現代文学がかかえる大きな問題そのものになっている。
さらにいえば、大岡の死の1年後に刊行された『昭和末』には、そのエンタテイメントの新しい姿をとらえて、以前とは異なった模索が語られている。
すなわち、私には「大岡昇平の時代」はけっして終わっていないのだ。
『大岡昇平の時代』
湯川 豊
河出書房新社
312頁、2,300円(税抜)
※所属・職名等は本誌発刊当時のものです。
- 1
| カテゴリ | |
|---|---|
| 三田評論のコーナー |

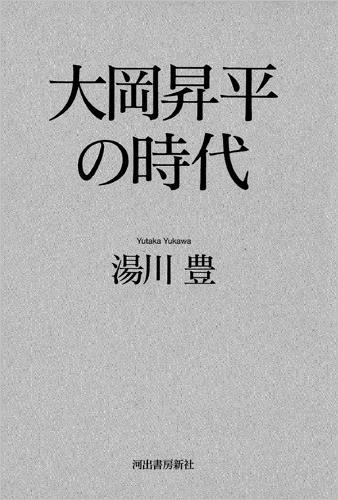
湯川 豊(ゆかわ ゆたか)
文芸評論家・塾員